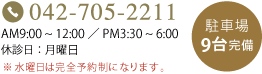犬と猫の膵炎について|早期発見・早期治療が大切な疾患
愛犬や愛猫が突然吐いてしまったり、なんとなく元気がなかったりすることはありませんか?
一見すると胃腸のトラブルのように見えても、実は「膵炎(すいえん)」が原因になっていることがあります。
膵炎は、軽い症状でおさまる場合もあれば、命に関わるほど重症化してしまうこともある病気です。だからこそ、早めに気づいて治療を始めることがとても大切になります。
今回は、犬と猫の膵炎の主な症状や考えられる原因、治療の方法などについて解説します。

■目次
1.膵臓に起こる炎症“膵炎”ってどんな病気?
2.膵炎の症状と見分け方
3.膵炎が起こる理由
4.診断方法
5.治療法
6.日常での注意点と予防
7.おわりに|早期受診の重要性
1.膵臓に起こる炎症“膵炎”ってどんな病気?
膵臓は、胃の後ろ側に位置する臓器で、体の中でとても大切な2つの働きを担っています。
ひとつは、食べ物の消化を助ける酵素を作る「外分泌機能」。もうひとつは、血糖値を調節するインスリンなどのホルモンを分泌する「内分泌機能」です。
「膵炎(すいえん)」とは、この膵臓に炎症が起きてしまう病気です。
通常、膵臓で作られた消化酵素は、腸(十二指腸)に届いてから初めて働きはじめ、食べ物の消化に関わります。けれど、何らかの原因でこれらの酵素が膵臓の中で活性化してしまうと、膵臓自身を傷つけてしまい、炎症を起こしてしまうのです。これが「自己消化」と呼ばれる状態です。
膵炎には大きく分けて「急性膵炎」と「慢性膵炎」の2つのタイプがあります。
<急性膵炎>
ある日突然発症し、重症化すると命に関わることもある、緊急性の高い疾患です。
なお、犬では急性膵炎が多く、猫ではほとんどみられないことが知られています。
<慢性膵炎>
急性膵炎のようなはっきりした症状が現れにくいこともありますが、膵臓に炎症がじわじわと急性膵炎のような特徴的な症状が現れないことも多く、何となく元気や食欲がないなど他の疾患でみられるような漠然とした症状だけの場合もあり、膵炎と気づきにくいことがあります。
2.膵炎の症状と見分け方
膵炎の症状はとても幅広く、軽いものから重いものまでさまざまです。
特に初期の段階では、急性胃腸炎などの消化器系の病気とよく似た症状が出るため、見分けがつきにくいこともあります。
<急性膵炎の主な症状>
急性膵炎でもっとも特徴的なのが、繰り返し吐くことです。通常の胃腸炎とは違って、吐く回数が多く、なかなか止まらないのが特徴です。
そのほか、以下のような症状が見られることがあります。
・食欲が落ちる、またはまったく食べなくなる
・お腹に強い痛みがあり、触られるのを嫌がる/背中を丸める
・元気がなくなる、動かなくなる
・下痢(血便を伴う場合がある)
・脱水症状(口の中が乾いている、皮膚のハリがなくなる)
・発熱
特に痛みが強いと、「祈りのポーズ」と呼ばれる前足を伸ばしてお尻を上げる姿勢をとることがあります。これは、お腹が床に触れるのを避けようとする仕草です。
<劇症型膵炎の症状>
膵炎の中でも特に重篤な劇症型膵炎では、次のような危険な症状が現れることがあります。
・ぐったりして動かない(虚脱)
・呼吸が荒くなる、息苦しそうになる
・ショック症状(足先が冷たい、歯ぐきが白っぽい)
・出血が止まりにくい(凝固障害によるもの)
劇症型膵炎は進行がとても早く、数時間〜数日で命に関わる状態になることもあるため、これらの症状が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください。
<猫の膵炎の特徴>
猫の場合は、犬と比べて症状がはっきり出ないことが多く、気づきにくい傾向があります。
・嘔吐の回数が少ない、あるいは見られないこともある
・食欲が落ちる、元気がなくなるなど、はっきりしない症状が中心
・急激に悪化することは少なく、慢性的にじわじわ進行することが多い
猫は体調が悪くても我慢してしまう動物です。「なんとなく変だな」と思ったときこそ、早めにご相談いただくことが大切です。
3.膵炎が起こる理由
膵炎は、はっきりとした原因が分からないことも多く、「特発性(とくはつせい)」=原因不明と診断されることが少なくありません。
ただし、いくつかの要因が関係している可能性があり、以下のようなケースが報告されています。
◆食事の影響
脂肪分の多い食事をしたあとに膵炎を起こすことがありますが、実際にはそれほど多くはありません。
ただし、人の食べ物(特に脂っこいもの)を与えたあとに発症したという報告もあります。
◆代謝の異常
血液中の脂肪が多い「高脂血症」などが、膵炎のリスク要因になることがあります。ただし、すべての膵炎に関係しているわけではありません。
◆薬の影響
一部の薬剤が、まれに膵炎を引き起こすことがあります。
◆感染症
ウイルスや細菌による感染が関係しているケースもあります。
◆遺伝的な要因
特定の犬種(たとえばコッカー・スパニエル、ミニチュア・シュナウザーなど)は、膵炎を起こしやすい傾向があるといわれています。
◆ほかの病気との関係
糖尿病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などの内分泌疾患との関連も指摘されています。特に猫の膵炎は糖尿病と関連して発生するともいわれており、幅広い年齢での発症が報告されています。
糖尿病についてはこちらから
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)についてはこちらから
このように、いろいろな要因が考えられるものの、実際のところ原因を特定できないケースが多いのが現状です。
そのため、原因の特定にこだわりすぎず、少しでも早く異変に気づいて適切な治療を始めることが大切です。
早期に対応することで、回復の可能性がぐっと高まります。
4.診断方法
膵炎を正確に診断するためには、いくつかの検査を組み合わせて行うことが必要です。
主な検査には、以下のようなものがあります。
◆血液検査
膵臓の酵素(アミラーゼやリパーゼ)や、体内の炎症の程度を示すマーカーを調べます。
◆特殊検査(膵臓特異的リパーゼ)
犬ではcPL、猫ではfPLという膵臓に特有の酵素を測定する検査で、膵炎の診断にとても有用です。
◆画像検査(超音波検査やレントゲン)
膵臓の腫れや周囲の臓器との関係、腹水の有無などを確認するために行います。
これらの検査結果に加えて、日頃の様子や見られている症状を総合的に判断して診断を行います。
「この検査だけで確定する」というよりは、いくつかの情報を組み合わせて、慎重に見極めていきます。
5.治療法
膵炎の治療は、症状の重さや愛犬・愛猫の状態に応じて内容が変わります。
基本的には以下のような治療を組み合わせて行います。
<軽度〜中等度の場合>
比較的軽い膵炎では、以下のような治療を行うことで回復が期待できます。
・輸液療法(点滴):脱水を改善し、体の循環をサポートします。
・制吐剤の投与:繰り返す嘔吐をおさえて体力の消耗を防ぎます。
・鎮痛剤の使用:膵炎による腹痛をやわらげます。
・抗生物質:感染が疑われる場合や重なっている可能性があるときに使用されます。
・一時的な絶食と食事の再開:消化器を休ませるため、初めは絶食し、その後は消化にやさしい低脂肪食から少しずつ再開していきます。
<重度の場合>
状態が重い膵炎では、入院して集中的な治療が必要になることがあります。
・集中的な輸液管理
・強い痛みに対する鎮痛ケア
・酸素吸入:呼吸状態が悪化した場合には、酸素を使ってサポートします。
・血圧・凝固のモニタリング:ショックや出血傾向がある場合は、継続的な管理が必要です。
・輸血(必要に応じて)
・栄養サポート:長期間食べられない場合は、静脈栄養などで必要なエネルギーを補います。
膵炎の治療では、何よりも「早く治療を始めること」がとても大切です。
軽度の膵炎であれば、数日で元気を取り戻すケースもありますが、重度の場合は時間をかけた集中治療が必要になることもあります。
6.日常での注意点と予防
膵炎を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、日頃のちょっとした心がけで発症のリスクを減らすことは可能です。
毎日の生活の中で、以下のようなポイントに気をつけましょう。
◆食事管理
まずは、栄養バランスのとれたフードを選び、愛犬・愛猫に合った量を与えるようにしましょう。脂っこい食べ物は膵臓への負担が大きくなるため、人の食べ物などは与えないように注意が必要です。
また、フードの種類を急に変えることも消化器にストレスを与える原因になるため、切り替えるときは少しずつ慣らしていくことが大切です。
さらに、おやつの与えすぎにも気をつけましょう。ごほうびとして少量与える分には問題ありませんが、ついつい量が増えてしまうと、カロリーオーバーや脂肪の摂りすぎにつながることがあります。
◆健康管理
年に1〜2回は健康診断を受けて、膵臓を含めた全身の状態を確認しておくと安心です。また、肥満は膵臓に負担をかける一因となるため、適正な体重を保つように心がけましょう。
さらに、糖尿病などの基礎疾患がある場合は、その病気のコントロールが膵炎の予防にもつながります。定期的な通院やお薬の管理をしっかり行うことが、体全体の健康維持に役立ちます。
◆ 日頃の観察
毎日のちょっとした様子の変化に気づいてあげることも、膵炎の早期発見につながります。普段と比べて元気がない、食欲が落ちている、なんとなく動きが鈍いなど、些細な変化でも「いつもと違うな」と感じたら注意が必要です。
少しでも気になることがあれば、無理に様子を見続けず、早めに動物病院を受診しましょう。
7. おわりに|早期受診の重要性
膵炎は、軽い症状で済むこともありますが、ときには命に関わるほど重症化することもある病気です。特に「劇症型」と呼ばれる膵炎では、体調が急速に悪化するケースもあり、迷っているうちに重篤な状態になってしまうこともあります。
にゅうた動物病院では、犬や猫の膵炎に対する診断・治療に力を入れており、一頭一頭の状態に合わせたサポートを大切にしています。
ほんの小さな変化でも、お気軽にお声かけください。早期の治療開始が、大切なご家族の健康を守る第一歩になります。
にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院
診療内容についてはこちらから