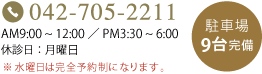【猫の肥大型心筋症】初期は症状が出にくい…?知っておきたいサインと対策
「うちの子、最近ちょっと呼吸が速い気がする…」「食欲がないのは年のせい?それとも病気?」そんな風に感じたことはありませんか?
猫の心臓病の中でも特に多い「肥大型心筋症(HCM)」は、初期には目立った症状が出にくいため、発見が遅れてしまうことが少なくありません。ですが、定期的な検診や早めのチェックによって、命に関わるリスクを減らすことができる病気です。
今回は、肥大型心筋症の特徴や原因、初期に見られる小さなサイン、検査や治療の流れ、そして日常生活で注意したいポイントについて解説します。

■目次
1.肥大型心筋症ってどんな病気?
2.こんな症状に注意!初期サインとは
3.原因は?どんな子がなりやすい?
4.どうやって見つける?検査と診断方法
5.治療の目的は「悪化を防ぐこと」
6.循環器の専門医が診療を行っています
7.おわりに
1.肥大型心筋症ってどんな病気?
猫の心臓は筋肉でできています。その筋肉が通常よりも分厚くなると、心臓が十分に広がらなくなり、体に必要な血液を送り出せなくなります。これが「肥大型心筋症(HCM)」です。
猫の心臓病の中でも特に多く見られる病気で、純血種に発症が多いとされていますが、雑種の猫にも起こり得ます。初期は症状が目立たないことが多いため、注意が必要です。
2.こんな症状に注意!初期サインとは
肥大型心筋症は、初期には無症状のことが多い病気ですが、次のような小さな変化が現れる場合があります。
・呼吸が浅く速くなる
・食欲や元気が落ちる
・心雑音(動物病院での聴診で指摘されることがあります)
進行すると、肺水腫、不整脈、咳が出るほか、突然後ろ足が動かなくなる「動脈血栓塞栓症」といった重い症状を起こすこともあります。
「ちょっと様子が変かも」と感じたら、早めに病院で相談することが大切です。
3.原因は?どんな子がなりやすい?
肥大型心筋症の原因は、主に遺伝的な要因が関わっていると考えられています。特に以下の猫種では発症リスクが高いことが知られています。
・メインクーン
・アメリカンショートヘア
・ラグドール
・ペルシャ
遺伝の影響が大きいとはいえ、雑種の猫にもみられることがあります。そのため「うちの子は大丈夫」と決めつけずに、定期的な心臓のチェックを受けることが大切です。
4.どうやって見つける?検査と診断方法
無症状で進行することが多いため、健康診断や心臓検査で初めて見つかるケースも少なくありません。主な検査方法は次のとおりです。
・聴診:心雑音の有無を確認
・心エコー検査:心筋の厚さや動きを観察
・レントゲン検査:心臓の大きさや肺の状態を確認
レントゲン検査・エコー検査について詳しくはこちらで解説しています
特に純血種やシニア猫は、年1回以上の心臓検査をおすすめします。
5.治療の目的は「悪化を防ぐこと」
肥大型心筋症は、完治が難しい病気です。そのため、治療の目的は症状を和らげ、進行を遅らせることにあります。
・飲み薬による治療(心拍数や血圧をコントロール)
・抗血栓薬による血栓予防
・定期的な検査による経過観察
症状が出ていない場合でも、半年〜1年ごとの検査を続けることが大切です。
6.循環器の専門医が診療を行っています
当院では、日本獣医循環器学会が認定する「獣医循環器認定医」が定期的に診療を担当しています。循環器分野に特化した知識と経験を持つ獣医師が関わることで、愛猫の心臓病に不安を抱える飼い主様にとっても、より安心してご相談いただける体制を整えています。
こうした豊富な経験をもとに、心雑音やエコーの所見といった小さな変化も丁寧に確認し、その子の状態に合わせた治療方針をご提案します。「無症状だけど心配…」という段階からご相談いただくことで、より早い診断や適切なサポートにつながります。
7.おわりに
肥大型心筋症は、症状が目立ちにくいまま進行してしまう心臓病です。だからこそ、呼吸の速さや元気・食欲の低下など、日常のちょっとした変化に気づくことが大切です。
早めに検査を受けて状態を把握しておくことで、進行を抑えながら愛猫の穏やかな時間を守れるケースもあります。にゅうた動物病院では、飼い主様と猫の暮らしを支えるために、専門的な検査・治療を含めた診療体制を整えています。
「少し気になるかも…」という段階でのご相談が、早期発見と適切なケアにつながります。どうぞお気軽にお声がけください。
■関連する記事はこちら
・シニア期の犬や猫の健康管理|定期健診でできる予防と早期発見の重要性
・定期的な健康診断①
・定期的な健康診断②「身体検査について」
・定期的な健康診断③「血液検査について」
にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院
診療内容についてはこちらから