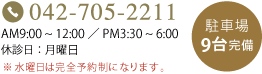犬の血小板減少症について|愛犬の命を守るために知っておきたいこと
犬の血小板減少症は、早期に発見し適切な治療を受けることで改善が期待できる病気です。しかし、進行すると命に関わるリスクもあるため、愛犬の健康に日頃から目を向けることがとても大切です。
今回は、犬の血小板減少症について、よく見られる症状やその原因を詳しく解説するとともに、当院で行っている治療方法についてもお伝えします。

■目次
1.血小板減少症とはどんな病気?
2.気をつけたい症状と心配な時の対応
3.血小板減少症の種類と原因
4.どんな検査が必要?
5.治療法
6.日常での注意点
7.よくある質問
8.おわりに
1.血小板減少症とはどんな病気?
血小板は、「傷ができたときに出血を止める」という非常に重要な役割を担っています。健康な状態では、血液中に十分な量(20〜50万/μl)の血小板が含まれていますが、何らかの理由でこの数が大幅に減少してしまうことがあります。これが「血小板減少症」という状態です。
血小板が不足すると、ちょっとした傷でも出血が止まりにくくなり、場合によっては命に関わるような深刻な状態に発展することがあります。
特に犬の場合は、自己免疫の異常が原因で起こる「免疫介在性血小板減少症」が多く見られるのが特徴です。この病気では、免疫が誤って自分の血小板を敵とみなし、攻撃してしまうため、血小板の数が減少してしまいます。
2.気をつけたい症状と心配な時の対応
血小板減少症は、早期に気づいて適切に対処することで改善が期待できる病気です。
愛犬の体に以下のような症状が見られた場合は、決して放置せず、早めに動物病院に相談しましょう。
・お腹や脇の下、太ももの内側などの皮膚の薄い部分に、小さな赤い点や青あざが見られる
・歯茎から出血している、または歯茎に小さな赤い点がある
・鼻血が出やすい、または出血が止まらない
・元気がなく、食欲が低下している
・歯茎や舌が青白っぽくなっている
3.血小板減少症の種類と原因
血小板減少症には、大きく分けて2つのタイプがあります。
<免疫介在性血小板減少症>
このタイプは最も多く見られ、免疫システムが自分の血小板を異物と誤認して攻撃することが原因で発症します。主な特徴は以下の通りです
・メス犬に多い
発症例の約7割がメス犬です。
・特定の犬種で発症しやすい
コッカー・スパニエル、トイ・プードル、シー・ズーなどが特に発症しやすいとされています。
・中年以降の犬に多い
加齢が影響している可能性があるため、中年以降の犬では注意が必要です。
<その他の原因による血小板減少症>
免疫の異常以外の原因で血小板が減少する場合もあります。考えられる原因は以下の通りです。
・感染症
細菌やウイルスの感染が引き金となることがあります。
・薬の副作用
一部の薬剤が血小板に影響を及ぼすことがあります。
・腫瘍などの病気
内臓や血液の腫瘍が血小板の減少に関わることがあります。
・その他の基礎疾患
血液の病気や他の全身疾患が原因となることもあります。
4.どんな検査が必要?
身体検査で皮膚のあざや歯茎の出血が見られる場合、血小板減少症が疑われます。その際には、以下のような検査が行われます。
・血液検査
血液中の血小板の数や状態を確認します。また、血液に他の異常がないかを詳しく調べ、診断に役立てます。
また、血液塗抹標本(血液を薄く伸ばして顕微鏡で観察する検査)を作成し、細胞の種類や形態を調べることもあります。
・画像検査(必要に応じて)
レントゲンや超音波検査を行い、内臓の異常や隠れた疾患がないかを確認します。この検査では、血小板減少の原因が血液以外にあるかどうかも調べることができます。
5.治療法
血小板減少症の治療は、症状や原因に応じて異なります。愛犬の状態に合わせて、以下のような治療を進めていきます。
・免疫抑制剤の使用
免疫システムの異常を抑えるため、ステロイドなどの免疫抑制剤を使用します。
・必要に応じた入院治療
症状が重い場合や継続的な管理が必要な場合には、入院治療が行われます。入院中は、出血のコントロールや全身の状態を細かく観察しながら治療を進めます。
・定期的な経過観察と検査
治療の効果や血小板の数を確認するため、定期的な検査が必要です。経過を見ながら治療内容を調整し、愛犬の健康を守ります。
治療期間は愛犬の症状や治療への反応によって異なりますが、適切な治療を続けることで多くの場合、症状の改善が期待できます。
6.日常での注意点
血小板減少症は残念ながら完全に予防することが難しい病気ですが、日々の生活の中で注意を払うことで、早期発見や健康管理につなげることができます。
・定期的な健康診断
年に2回程度、動物病院で健康診断を受ける習慣をつけましょう。獣医師による診察では、血液検査や身体検査を通じて、普段は気づきにくい異変をチェックしてもらうことができます。
・普段から愛犬を丁寧に観察する
愛犬の体をこまめに観察することも、健康を守る大切なポイントです。たとえば、お腹や脇の下など、皮膚が薄い部分を週に1回程度確認してみましょう。小さな赤い点や青あざがないかを観察することで、異変に早く気づくことができます。
また、お散歩から帰った後には、全身を確認する習慣をつけましょう。怪我や出血がないか、普段と違う様子がないかもチェックポイントです。
さらに、歯磨きの際には歯ぐきの色や状態も忘れずに確認してください。赤い点や出血がないか、歯ぐきの色が青白くなっていないかを見ることで、健康状態の変化を早期にキャッチできる可能性があります。
・過度な運動を避ける
激しい運動や体に大きな負担がかかる活動は、愛犬に思わぬ影響を与える可能性があります。特に血小板が少ない場合には、体内での出血リスクが高まるため注意が必要です。
よくある質問
Q:完治する病気でしょうか?
A:血小板減少症は適切な治療を続けることで多くの場合、症状をコントロールすることが可能です。ただし、再発のリスクがあるため、治療後も定期的な検査や観察が欠かせません。
Q:予防接種は受けられますか?
A:症状が落ち着いている場合には、予防接種を受けることが可能です。ただし、愛犬の体調や治療状況によって判断が必要ですので、主治医としっかり相談しながら進めることをおすすめします。
おわりに
私たち、にゅうた動物病院では、愛犬の健康を支えるために、丁寧な診療と寄り添うケアを心がけています。
血小板減少症に限らず、愛犬の体調や行動に少しでも気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。日々の健康管理から病気の早期発見、治療、そして予防まで、愛犬一頭一頭の個性や状態に合わせたケアを大切にしています。
飼い主様と愛犬が安心して暮らせる毎日をサポートするため、これからも全力で取り組んでまいります。
■関連する記事はこちらで解説しています
・犬の溶血性貧血について|気づかないと命に関わることも
にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院
診療内容についてはこちらから
※本記事の内容は、最新の獣医療の知見に基づいています。ただし、個々の症例により適切な治療法は異なります。ご心配な点がございましたら、お気軽に当院までご相談ください。
<参考文献>
Immune thrombocytopenia (ITP): Pathophysiology update and diagnostic dilemmas - LeVine - 2019 - Veterinary Clinical Pathology - Wiley Online Library
Treatment and predictors of outcome in dogs with immune-mediated thrombocytopenia in: Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 238 Issue 3 () (avma.org)