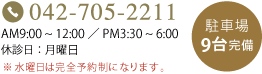犬・猫の尿管結石摘出|内科治療・バイパス手術との違いと選択基準を獣医師が解説
犬や猫の泌尿器トラブルの中でも「尿管結石」は注意すべき病気のひとつです。尿管が結石で塞がれてしまうと尿の流れが止まり、腎臓に大きな負担がかかって命に関わることもあります。
治療法には内科治療(食事療法・薬による管理)、外科的な摘出手術、尿管バイパス手術などがあります。いずれも「どれか一つが正解」というものではなく、犬や猫の状態・結石の大きさや位置・全身の健康状態を総合的に判断して選ぶことが大切です。
今回はその中でも「尿管結石摘出手術」に焦点をあて、どのような場合に適応されるのか、他の治療法との違い、そして術後の管理について解説します。

■目次
1.摘出手術が適応となるケースとタイミング
2.摘出手術の術式と技術的なポイント
3.他の治療法との比較と使い分け
4.術後の回復過程とご家庭での注意
5.長期的な予後と再発防止
6.おわりに
1. 摘出手術が適応となるケースとタイミング
まずお伝えしたいのが、摘出手術はあくまで数ある治療選択肢のひとつだということです。結石が小さく、尿の流れが保たれている場合はまず内科治療を選択する事もあります。
一方で、次のようなケースでは摘出手術を検討する必要があります。
・結石が大きく、内科治療で小さくできない、あるいは尿管の大部分を塞いでしまっている
・尿管の損傷が軽度で、結石を除去すれば機能回復が見込める
・内科治療に反応せず、閉塞や症状が長期化している
結石による閉塞は腎臓に急速なダメージを与えるため、こうした状況では早急な手術対応が命を守ることにつながります。
2. 摘出手術の術式と技術的なポイント
尿管結石の摘出は、全身麻酔下で行う外科手術です。基本的には「尿管切開術」という方法が用いられ、以下のような流れで進みます。
①術前検査
血液検査や画像検査で、結石の位置・大きさ・数を確認します。同時に腎臓や全身の状態をチェックし、手術に耐えられるかどうかを慎重に確認します。
②開腹と尿管切開
お腹を開いて尿管にアプローチし、結石のある部分を切開します。
③結石の摘出と尿管機能の確認
結石を取り除いたあと、カテーテルを通して液体を流し、尿管が開通しているかを確認します。この工程で「尿がきちんと流れる状態を確保できているか」を判断することが重要です。
④縫合と閉腹
尿管を丁寧に縫合し、漏れがないことを確認してからお腹を閉じます。縫合の確実さは術後合併症を防ぐための大切なポイントです。
処置時間はおおよそ1〜2時間程度で、結石を確実に除去しながら尿管へのダメージを最小限に抑える高度な技術が求められます。
当院では、術中に細かな確認を徹底し、尿管の損傷や尿の漏れを防ぐための縫合技術に細心の注意を払っています。これにより、手術の安全性を高め、術後の合併症リスクをできる限り抑えることを大切にしています。
3. 他の治療法との比較と使い分け
尿管結石の治療は「手術ありき」ではなく、症例ごとに最適な方法を選ぶことが大切です。当院では内科治療・摘出手術・バイパス手術を含めた幅広い選択肢を視野に入れ、総合的に判断しています。
◆内科治療が優先されるケース
結石が小さく、食事療法で溶解や縮小が期待できる場合、あるいは尿の流れが保たれていて症状が出ていない場合には、まずは体への負担が少ない内科治療を行うことが多いです。
ただし、大きな結石や完全閉塞のケースでは限界があるため、外科治療へ切り替える必要があります。
◆摘出手術が適応となるケース
結石が尿管を塞いで腎臓に負担をかけている場合には、摘出手術による直接的な除去が有効です。ただし、再発や術後管理が必要となるため、長期的な視点でのケアを欠かすことはできません。
◆バイパス手術が選択されるケース
尿管に強い炎症がある場合、結石が繰り返しできる場合、または両側の尿管が閉塞している場合には、摘出手術だけでは解決が難しいことがあります。そうしたケースでは、腎臓と膀胱をチューブで直接つなぐバイパス手術を検討します。
当院では、術中に尿管の状態を確認し、摘出が困難と判断した際には速やかにバイパス手術へ切り替える体制を整えています。
このように、尿管結石の治療は一つの方法に固執せず、症状や進行度、愛犬・愛猫の体調を踏まえて柔軟に判断することが重要です。私たちは常に「その子にとって最も適した方法」を見極めながら治療方針を決定しています。
4. 術後の回復過程とご家庭での注意
尿管結石の摘出手術を受けたあとは、しっかりと回復を支えるために術後管理が欠かせません。
<入院期間と回復の目安>
手術後は5日~1週間程度の入院が必要です。その間、縫合部から尿の漏れがないか、腎臓の機能が順調に回復しているかを丁寧に確認します。
<術後の痛み管理と抗炎症治療>
入院中は鎮痛剤や抗炎症薬を使用して痛みや炎症を抑え、落ち着いて回復できるようにサポートします。これにより、術後のストレスや体への負担を最小限に抑えることができます。
<尿管の癒合と機能回復のモニタリング>
術後は尿管がしっかり閉じて機能を回復しているかを確認するために、尿の通り道や腎臓の働きを継続的にチェックします。縫合部分の安定性や尿の流れを確認することは、再閉塞や炎症を防ぐうえで非常に重要です。
<退院後のご家庭でのケア>
退院したあとは以下の点に注意して観察してください。
・尿の色・量・回数に変化がないか
・食欲や元気の有無、水分摂取量に異常がないか
・傷口の腫れや痛みが残っていないか
もし尿が出ない、血尿が続く、元気や食欲が落ちているなど気になる症状が見られた場合は、お早めにご相談ください。
5. 長期的な予後と再発防止
摘出手術で尿管の通り道が確保されても、その後の管理がとても重要になります。再発のリスクや腎機能への影響を見据えて、長期的なケアを続けることが愛犬・愛猫の健康を守るポイントです。
◆腎機能の回復と注意点
結石による急性の腎障害は、手術で尿管が開通すると回復することが多いですが、中には慢性腎臓病へ移行するケースもあります。術後も腎機能の数値を継続的にチェックし、早期に変化をとらえることが大切です。
◆結石の成分分析と食事療法
摘出した結石を分析することで、形成の原因を明らかにできます。その結果に基づいて、再発を防ぐための食事療法をご提案します。フードの選択や水分摂取の工夫は、今後の予防に直結する重要なケアです。
◆定期的な検査で早期発見を
尿検査や超音波検査を定期的に行うことで、新たな結石の兆候や腎機能の変化をいち早く確認できます。小さな異変を早めにとらえられるよう、継続的な健診をおすすめします。
◆内科的管理との組み合わせ
長期的な管理には、内科治療を併用することも効果的です。食事療法や投薬を組み合わせることで、再発リスクを抑えつつ、愛犬・愛猫が快適な暮らしを維持することにつながります。
6. おわりに
尿管結石の摘出手術は、適応を正しく見極めれば結石を根本的に取り除ける、有効な治療法のひとつです。ただし常に第一選択ではなく、内科治療やバイパス手術と比較しながら、その子の状態に最も適した方法を選ぶことが大切です。
当院では、手術だけにこだわらず、内科治療やバイパス手術も含めた幅広い選択肢をご提示し、飼い主様と一緒に最善の治療法を検討しています。また、治療後も定期的な検査や食事管理などを通じて再発防止に取り組み、長期的な健康維持をサポートいたします。
■関連する記事はこちら
・犬と猫の尿路結石症について|以前よりトイレの回数が増えたら要注意
・犬と猫の急性腎障害について|進行が早く早急な治療が重要
・犬や猫の慢性腎臓病について|進行するまで症状がわかりづらい病気
・犬と猫の膀胱炎について|犬と猫で多い病気の1つ
にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院
診療内容についてはこちらから