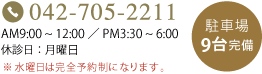犬の歯が折れたら「抜歯」しかない?歯内治療という選択肢とそのメリット
「歯が折れたら、抜歯するしかない」と思っていませんか?実は、条件を満たせば歯を残すことができる「歯内治療」という選択肢もあります。
歯内治療には、大きく分けて「覆罩術(ふくとうじゅつ)」と「抜髄根管治療(ばつずいこんかんちりょう)」があり、歯の状態によって適切な方法が選ばれます。
歯が折れた状態を放置すると、痛みや感染が広がるリスクがあり、愛犬の生活の質(QOL)にも悪影響を及ぼすこともあるため、注意が必要です。
今回は、歯が折れたときに考えられるリスクや治療の選択肢、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

■目次
1.犬の歯が折れるとどうなる?放置が危険な理由
2.歯内治療とは?歯を残すための高度な歯科治療
3.歯内治療と抜歯、それぞれのメリット・デメリット
4.おわりに
1. 犬の歯が折れるとどうなる?放置が危険な理由
<歯が折れる主な原因>
犬の歯は、表面がエナメル質という非常に硬い組織で覆われており、簡単には欠けたり折れたりしません。しかし、次のような状況では歯に強い力がかかり、破損することがあります。
・硬すぎるおもちゃや骨、石などを噛んだとき
・高いところから落ちる、ぶつかるなどのケガ
・加齢によって歯や歯周組織が弱くなっている場合
いずれもご家庭でも起こりうる身近な原因ばかりです。
<放置することで起こるリスク>
歯が折れても、すぐに見た目や体調に大きな変化が出るとは限りません。そのため「元気そうだから大丈夫」と様子を見てしまうこともありますが、外からはわからない場所で問題が進行していることがあります。
◆歯の内部で進行するダメージ
折れた部分から細菌が入り込むと、神経や歯根に炎症が起こり、痛みや腫れ、膿のたまりなどにつながることがあります。進行すれば周囲の組織にまで影響を及ぼすこともあります。
◆全身への影響も
口腔内のトラブルは、噛みにくさや食欲不振、ストレスの原因となり、結果的に体調全体へ影響を及ぼすことがあります。放置することで、他の病気の引き金になるおそれもあるため注意が必要です。
<気をつけたいサイン>
以下のような様子がみられた場合、歯のトラブルが隠れているかもしれません。
・食べにくそうにしている
・片側の歯だけで噛んでいる
・フードを丸飲みしてしまう
・食欲が落ちた/食べたがらない
・口周りを気にするような仕草がある
歯のトラブルは、早期に対応すれば歯を残せる可能性が高くなります。「少し気になるけれど、元気はあるから様子を見よう」と判断する前に、まずは一度、動物病院で状態を確認してもらうことをおすすめします。
2. 歯内治療とは?歯を残すための高度な歯科治療
「歯が折れたらもう抜歯しかない」と思われがちですが、歯の状態によっては、抜歯せずに治療することも可能です。そうした歯を保存するための処置が「歯内治療」です。
歯内治療には、大きく2つの方法があります。歯の内部にある神経(歯髄)がまだ生きている場合には「覆罩術」、すでに神経が損傷している場合や感染が広がっている場合には「抜髄根管治療」が行われます。
<覆罩術とは?>
覆罩術は、歯が欠けた際に神経の露出が最小限で済んでおり、なおかつ炎症が起きていないと判断される場合に選択される治療法です。
歯髄を温存しながら、露出部に薬剤を置き、その上から詰め物などで封鎖します。処置が早ければ早いほど成功率が高いため、歯が折れてすぐに治療を受けることが重要です。
<抜髄根管治療とは?>
一方、すでに歯髄が露出して感染が疑われる場合には、抜髄根管治療が必要となります。
折れて露出した歯の中(歯髄)には血管や神経が通っていて、そこに細菌が入り込むと炎症や強い痛みの原因となります。この治療では、歯の中にある神経を取り除き、歯の根っこの通り道(根管)を丁寧に洗浄・消毒したうえで、薬剤を詰めて密封します。必要に応じて、詰め物や被せ物を行い、見た目や噛む機能を補う処置も行います。
抜髄根管治療は、いくつかのステップに分けて進めていきます。
◆診察
口の中の視診とレントゲン検査で、歯の折れ方や根の状態を確認します。
全身麻酔が必要なため、事前に血液検査を行うこともあります。
◆処置(全身麻酔下)
治療中に動いてしまうと危険なため、全身麻酔をかけたうえで慎重に処置を行います。
①神経を取り除く
②歯の根っこの通り道(根管)を丁寧に洗って消毒する
③薬剤を詰めて外から雑菌が入らないように密封する
必要に応じて詰め物や被せ物で表面を補強し、噛みやすさや見た目もカバーします。
◆術後ケア
術後は感染や痛みの有無を確認しながら、少しずつ食事や生活を通常の状態に戻していきます。
<適応になるケースと注意点>
この治療法が向いているかどうかは、歯の状態や口腔内の環境によって判断されます。
以下のようなケースが、治療の適応かどうかを見極めるポイントとなります。
・適応しやすい例:破折があり、歯周組織が健康な場合。破折からの経過時間によって「覆罩術」か「抜髄根管治療」を選択します。
・適応が難しい例:歯根が縦に割れている、歯周病が進行している、神経が壊死しているなどのケース。
歯内治療には専門的な機材と高度な技術が必要なため、対応できる動物病院は限られます。当院では事前検査とカウンセリングを行い、歯の状態や全身の健康状態を総合的に判断したうえで、歯内治療を含む複数の選択肢の中から、最適な治療法をご提案いたします。
3. 歯内治療と抜歯、それぞれのメリット・デメリット
折れた歯の治療では「できれば歯を残したい」というお気持ちがある一方で、抜歯が必要となるケースもあります。どちらが適しているかは、歯の状態や口腔内の環境、生活スタイルによって異なります。まずは、それぞれの治療の特徴を知っておくことが大切です。
◆歯内治療
可能であれば歯を残したいと考える方に選ばれる治療法です。
<メリット>
・歯を残せるため、噛みやすさや見た目を保ちやすい
・歯を支える組織への負担が少なく、噛み合わせのバランスが維持しやすい
・歯を失うことによるストレスや不安を軽減できる
<デメリット>
・治療に時間と費用がかかる
・全身麻酔や専用の器具が必要で、対応できる動物病院が限られる
・治療後も定期的なチェックが必要
・歯周組織の状態によっては、処置後に歯周病が進行し、結果的に抜歯が必要になることもある
◆抜歯
炎症や感染の広がりを防ぐために、抜歯が最善の選択となるケースもあります。
<メリット>
・比較的シンプルな処置で、治療期間が短い
・感染や炎症のリスクがなくなり、痛みから早く解放されやすい
・再発の心配が少なく、術後の管理もシンプル
<デメリット>
・噛みづらくなったり、食べ方に変化が出ることがある
・他の歯や顎に負担がかかる場合がある
・部位によっては見た目が気になることも
どちらが「正解」ということはなく、愛犬にとってのベストな選択は、状態やご家族の考え方によって異なります。大切なのは、歯の状態や生活環境、将来のケアまで含めて総合的に判断し、ご家族が納得できる選択をすることです。
4. おわりに
犬の歯が折れてしまったとき、必ずしも抜歯しか方法がないわけではありません。状態によっては、歯内治療という歯を残す選択肢もあることを知っておいていただければと思います。
ただし、破折した歯をそのまま放置すると、細菌感染や炎症が進行し、結果的に抜歯が必要になることもあります。できるだけ早い段階でのご相談が大切です。
また、歯の破折を防ぐためには、骨や鹿の角など非常に硬いものを噛ませないことも重要です。おもちゃや歯みがきガムを選ぶ際には、硬さに十分注意してください。
にゅうた動物病院では、愛犬の状態を丁寧に確認し、ご家族のご希望に沿った最善の治療をご提案しています。気になる症状があるときは、どうぞお気軽にご相談ください。
■歯科治療に関連する記事はこちら
・高齢犬の歯周病、「治療できない」と諦める前に|適切なケアで快適な生活をサポート
・犬と猫の歯周病について|ご家庭でのデンタルケアが予防に繋がる
・犬の歯石取りはいつすべき?|手術の流れと全身麻酔の安全性を解説
にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院
診療内容についてはこちらから